なぜホームページのリニューアルが必要なのか?
第一印象はホームページで決まる
人が何かを購入したり、サービスを利用したりする際、多くの場合まずは「ホームページ」を訪れます。
皆さんも何か物を購入するときはホームページを見に行ったことがある。という経験もあるのではないでしょうか?
最初の数秒で「この会社は信頼できそうか」「自分に合っていそうか」といった判断を無意識のうちに下しているのです。これはリアルな店舗の外観や、接客の第一声と同じように、企業の“顔”としての役割をホームページが担っているからです。
たとえば、次のようなケースでは第一印象が大きくマイナスに働くことがあります:
- デザインが古く、情報が雑然としている
- スマホで見たときにレイアウトが崩れている
- ローディングに時間がかかる
- 探したい情報がすぐに見つからない
このような状況では、ユーザーは「この会社、大丈夫かな?」という不安や不信感を持ってしまい、そのまま離脱してしまう可能性が高くなります。

逆に、デザインが洗練されており、情報が整理されていて使いやすいホームページは、「信頼できる」「丁寧な会社だ」「今どきの感覚がある」という良い印象を自然と与えることができます。これが問い合わせや資料請求、来店などのアクションにつながるきっかけになります。
つまり、ホームページの見た目や使いやすさは、単なる「デザインの問題」ではなく、売上や信頼に直結する“第一印象”の勝負なのです。
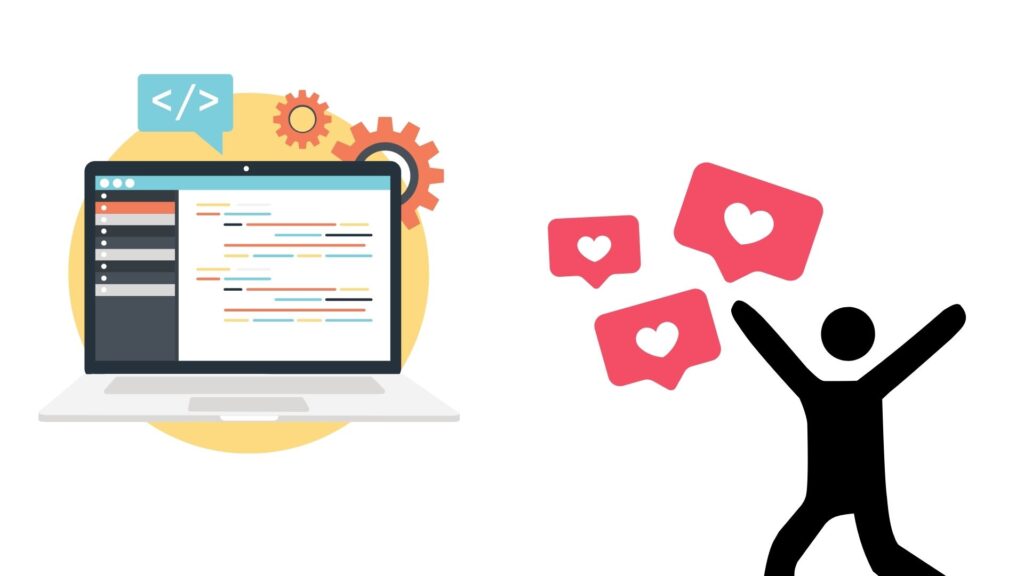
古いデザインや情報が信用を下げる理由
これまでホームページを見に行ったら、古!?となった経験はありませんか?
洗練されたデザインのホームページに見慣れてしまっている今の人たちはホームページが古いだけである種のアレルギー反応を起こしてしまう方も少なくはありません。
企業がどれだけ良い商品やサービスを提供していても、正しく伝わらなければ、ユーザーの信頼を得ることはできません。
古いホームページは、実際以上に会社の印象を悪くしてしまう「もったいない状態」なのです。
リニューアルを検討すべきサインとは?
デザインが時代遅れになっている
ホームページのデザインは、ファッションやインテリアと同じように*流行”があり、年々トレンドが変化しています。
しかし、何年も前に作ったホームページをそのまま使い続けていると、デザインが古く感じられ、ユーザーに「時代に取り残されている会社かも」というネガティブな印象を与えてしまうことがあります。
■ 時代遅れと判断される主なポイント
- 立体的なボタンやグラデーションが多用されている(今はフラットでシンプルなデザインが主流)
- Flashコンテンツが使われている(現在は多くのブラウザで非対応)
- 文字が小さい・行間が狭い(読みづらい印象を与え、スマホ閲覧にも不向き)
- 全体の配色が古くさく感じる(グレー背景や過剰な装飾など)
- 写真の画質が悪い、または画像が小さい
こうした“古さ”は、ユーザーに無意識のうちに「この会社は今のニーズや価値観に対応できていないのでは?」という不安を与えてしまいます。
スマホ対応ができていない・表示が崩れる
現在、多くの人がスマートフォンでインターネットを利用しており、ホームページへのアクセスの約半数以上がスマホからとも言われています。にもかかわらず、スマートフォンでの表示に最適化されていないホームページは、ユーザーに大きなストレスを与えてしまいます。
■ スマホ非対応サイトでよくある問題
- 文字が小さく、拡大しないと読めない
- ボタンやリンクが押しにくい・小さすぎる
- 横スクロールが必要で使いづらい
- 表示が崩れて、レイアウトがバラバラ
- 読み込みが遅く、すぐに離脱される
こうした問題があると、ユーザーは「見にくい」「使いにくい」と感じ、せっかくの訪問機会を逃してしまうことに繋がります。
■ モバイルファーストが当たり前の時代
Googleをはじめとする検索エンジンも、モバイル対応しているかどうかをランキング評価の基準にしているため、スマホ非対応のサイトはSEO(検索順位)でも不利になります。
つまり、「見にくいから離脱される」だけでなく、「そもそも見つけてもらいにくくなる」という二重のリスクがあるのです。

■ ユーザーの印象にも影響
スマホで見たときに、デザインが崩れていたり操作がしにくいサイトを見て、ユーザーが抱く印象は以下のようなものです:
- 「古い会社なのかな?」
- 「こういうところに気を使えてないってことは、他も大丈夫かな…?」
- 「信用できなさそう」
ホームページの見た目や使い勝手は、そのまま会社の印象に直結します。
更新が難しい・CMSが使いにくい
ホームページを運営していくうえで、「情報の更新」は欠かせません。新しい商品・サービスの紹介、キャンペーンのお知らせ、ブログの投稿、採用情報の変更など、タイムリーな更新ができることは信頼感や集客に直結します。
しかし、実際には以下のような課題を抱えているケースがよく見られます:
■ よくあるお悩み
- CMS(更新システム)が複雑で、社内の誰も使いこなせない
- HTMLや専門知識がないと更新できない設計になっている
- ちょっとした修正でも制作会社に依頼しないといけない
- 更新作業に時間がかかるので、結局後回しになってしまう
- 間違いがあってもすぐに直せない
このような状況が続くと、「更新が滞る → 情報が古くなる → 信頼を失う」という悪循環に陥ってしまいます。

■ CMSの使いやすさは運用効率に直結
最近のホームページ制作では、WordPressやWix、STUDIOなどの直感的に操作できるCMSが主流になってきています。
それでも、古いCMSや独自システムを使っていると、操作性が悪く、結局更新が止まってしまうというケースは珍しくありません。
「お知らせを追加するだけなのに、毎回操作方法を調べる」「画像を差し替えたいけどどこをいじればいいかわからない」――こういった状態では、せっかくのホームページを活かしきれず、情報発信の機会を逃してしまいます。
■ 更新がしやすいとは、ビジネスのスピードを上げること
CMSが使いやすくなれば、
- 社内でスピーディに情報発信できる
- お客様への情報提供がタイムリーに行える
- 外部依頼のコストや時間を削減できる
といったメリットがあり、運営の手間も減り、成果にもつながりやすくなります。
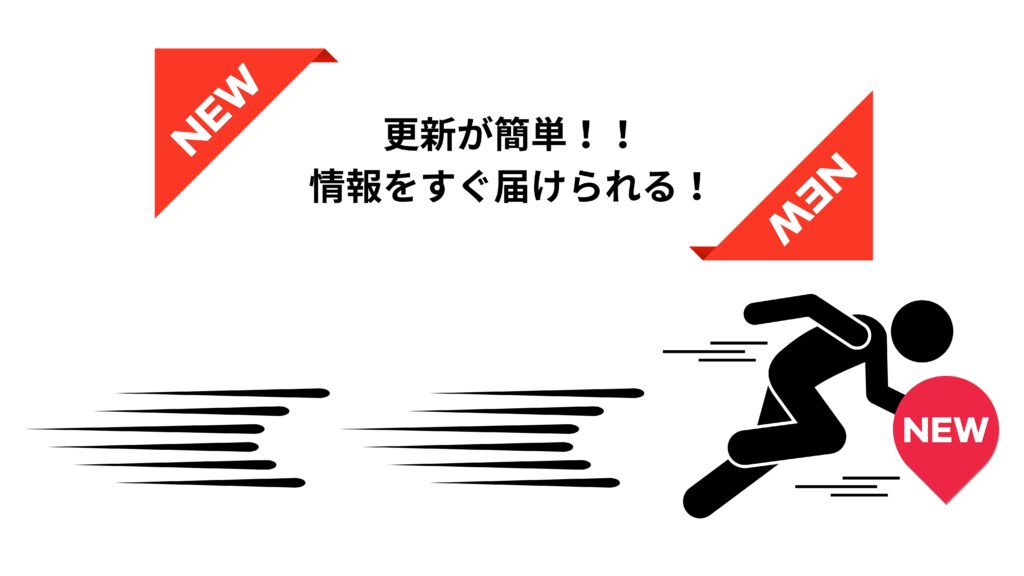
ホームページは“作って終わり”ではなく、“運用して育てていく”もの。
だからこそ、「誰でも、すぐに、簡単に更新できる」という仕組みづくりが重要なのです。
ビジネス内容が変化しているのにサイトが追いついていない
企業やお店の事業は、日々少しずつ変化していくものです。
新しい商品・サービスの追加、ターゲット層の見直し、拠点の拡大、業務内容の整理など、実際のビジネスが変わっているにもかかわらず、ホームページの内容が昔のまま止まっているケースは意外と多く見られます。
■ よくある「ズレ」の例
- メインで力を入れている商品が掲載されていない
- 既に終了しているサービスがまだ載っている
- 対象としている客層が以前と違うのに、表現が変わっていない
- ブランディングが刷新されたのに、サイトの雰囲気は昔のまま
- 新しい実績や導入事例が載っていない
このようなズレがあると、ホームページを見たお客様に間違った印象を与えてしまい、機会損失や誤解につながる恐れがあります。

■ ユーザーは「今のあなた(会社)」を知りたい
ホームページを見る人は、「この会社って何をしているの?」「どんな価値があるの?」ということを短時間で知りたくて訪問します。
そこで古い情報やズレた内容が表示されていると、次のような不安や不信感につながってしまいます:
- 「あれ?求めているサービスが見当たらない」
- 「この会社、今もちゃんとやってるのかな?」
- 「情報が古い=対応も古いのでは?」
つまり、ホームページとリアルのビジネスにギャップがある状態は、“信用の損失”にもつながるのです。
■ 今の事業内容に合ったサイトにすることのメリット
- お客様が“今の価値”を正しく理解してくれる
- 営業や採用で「話が早い」「信頼できる」という印象を持たれる
- 問い合わせや受注の質が上がる
- 自社スタッフのモチベーションアップにもつながる(自分たちの活動がきちんと発信されている)
ビジネスが進化しているのにホームページが古いままでは、自分で自分の価値を下げてしまうようなもの。
だからこそ、「今の自分たちを正しく伝える」ためのリニューアルは、タイミングを見てしっかり行うべきなのです。
リニューアルのベストなタイミングとは?
新商品・新サービスのリリース時
新しい商品やサービスをリリースするということは、企業にとって大きなチャンスであり、ユーザーとの新たな接点を生み出すタイミングでもあります。
ところが、ホームページがそれに対応していないと、そのチャンスを逃してしまうことにもなりかねません。

■ ホームページは“公式な情報源”
お客様にとって、企業のホームページは最も信頼できる情報源です。SNSや広告などで新サービスの存在を知ったとしても、多くの人は詳細を知るためにホームページに訪れます。
そこで情報がなかったり、見づらかったりすると、せっかくの興味も失われてしまいます。
■ よくある「準備不足」の例
- 新サービスの情報がホームページに載っていない
- 専用の紹介ページがなく、内容が分かりづらい
- 商品写真がない or 画質が低い
- 問い合わせフォームや導線が整っていない
- 旧商品との違いや強みが明確に打ち出されていない
こうした状態では、せっかくの新商品の魅力も十分に伝わらず、売上や問い合わせにつながりにくくなってしまいます。
■ リリース時は「見せ方」も重要
リニューアルの際には、ただ情報を載せるだけでなく、
- 専用のLP(ランディングページ)を作る
- 特集ページやバナーで目立たせる
- ビジュアルや動画を活用して魅力を表現する
- 比較や導入事例で分かりやすく伝える
といった見せ方の工夫が大切です。
また、スマホでの表示や読みやすさ、問い合わせボタンの配置なども意識し、ユーザーが「知って→理解して→行動できる」流れを作ることが成果につながります。
■ せっかくの投資を“最大限に活かす”ために
新商品や新サービスには開発コストやマーケティング費用がかかっているはずです。その成果を最大化するためにも、ホームページでの「魅せ方」や「導線づくり」は欠かせない要素と言えるでしょう。
新しい何かを始めたタイミングこそ、「今の自分たちを一番よく伝えられるホームページ」に整える絶好の機会なのです。
会社の方針転換・リブランディング時
企業は時代や市場の変化に合わせて、事業方針やブランドイメージを見直すタイミングが訪れます。
例えば、「BtoB中心から一般向けへシフトする」「エコ・サステナブルを軸にする」「価格帯やターゲットを再設定する」など、大きな方向転換をすることもあるでしょう。

こうしたタイミングで、ホームページの内容・デザイン・構成が従来のままでは、社内での変革が社外に正しく伝わらなくなってしまいます。
■ 「言っていること」と「見えていること」がズレてしまう
リブランディングの内容がメディアや広告で発信されていても、ホームページが昔のままだと、ユーザーは違和感を覚えます。
- メッセージは変わっているのに、デザインが古いまま
- 対象ユーザー層と合わないトーンやビジュアル
- ロゴやスローガンは新しくなったのに、反映されていない
- 掲載内容が以前の事業方針のままで統一感がない
このような状態では、せっかくのブランディング努力が台無しになってしまいます。
■ ブランドの“世界観”を一貫させるために
リブランディングとは、単に「見た目を変える」ことではなく、企業の想いや価値観、立ち位置を再定義し、それをあらゆる接点で伝えていくこと。
その中でもホームページは、名刺代わりであり“顔”とも言える重要な媒体です。
だからこそ、
- 新しいロゴやコピーに合わせたデザイン設計
- 色やフォント、トーン&マナーの統一
- 経営メッセージやミッション・ビジョンの発信
- 顧客層や市場に合わせた情報設計
など、全体の統一感をもって刷新することが必要になります。

■ ホームページは「変化を社外に伝える最初の窓口」
会社の方向性が変わったとき、社員や取引先だけでなく、見込み客・応募者・メディア関係者など、すべてのステークホルダーが最初に見るのがホームページです。
だからこそ、リニューアルによって、
- 「会社がどこを目指しているのか」
- 「何を大切にしているのか」
- 「誰に何を届けたいのか」
を明確に伝えることで、信頼感と共感を得ることができるのです。
方針転換やリブランディングのタイミングこそ、ホームページの価値が最も発揮されるとき。
「想いを正しく伝えられるサイト」にすることは、経営戦略そのものの一部とも言えるのです。
決算後、または新年度のスタート時期
年度が切り替わるタイミングは、企業にとってさまざまな変化が起こる節目です。
経営計画の見直し、目標設定、人事異動、新しいサービスやキャンペーンの準備など、「次のステージに向けた動き」が活発になるタイミングです。
そんな中で、ホームページも「気持ち新たに整える」べき大切な要素の一つです。
■ 情報をアップデートする絶好の機会
新年度には以下のような内容に変更が生じることがよくあります:
- 組織体制や代表者の変更
- 経営ビジョンやスローガンの刷新
- サービス内容・価格体系の見直し
- 採用情報・スタッフ紹介の更新
- お知らせや活動報告の整理
こうした変更がホームページ上に反映されていないと、社外との認識にギャップが生まれ、信頼感を損ねてしまうこともあります。
■ 1年のスタートに、情報とデザインをリフレッシュ
新年度のタイミングでリニューアルや情報更新を行うと、次のようなメリットがあります:
- 社内のモチベーションアップ(社員が「会社が進化している」と実感できる)
- 採用活動におけるブランド強化(求職者に最新の魅力を伝えられる)
- 既存顧客・取引先への信頼向上(事業の安定感や透明性が伝わる)
- 経営方針を社外にわかりやすく伝えられる(ミッションや目標を発信)
また、キャンペーンやイベントを展開する場合も、新年度のスタートにあわせてページをリニューアルすることで、印象づけや成果にもつながりやすくなります。
■ 気持ちを切り替えやすい“自然な区切り”として活用
ホームページのリニューアルは、日々の業務の中ではつい後回しにされがちです。
しかし「決算が終わったから」「新年度が始まったから」といった**“区切り”があると、社内でも動き出しやすく、関係者の合意も取りやすい**という利点があります。
ホームページを見直すことは、企業の「姿勢」や「本気度」を伝える手段のひとつ。
新しい期の始まりこそ、気持ちを一新し、会社の“今”と“これから”を正しく発信する絶好のチャンスです。

繁忙期を避けた落ち着いた時期
ホームページのリニューアルは、見た目のデザインだけでなく、構成の見直しや文章作成、写真撮影、システムの調整など、意外と手間と時間がかかるプロジェクトです。
そのため、日々の業務に追われる繁忙期に無理して取り組もうとすると、かえって中途半端になったり、スケジュールがズレ込んでしまったりというリスクもあります。
■ 落ち着いて取り組める=クオリティの高いサイトができる
比較的業務が落ち着いている時期を選べば、
- 内容の見直しにじっくり取り組める
- 写真や文章なども丁寧に準備できる
- 社内確認・フィードバックもしやすい
- チーム内の連携がスムーズになる
といったメリットがあり、結果的に「しっかりしたリニューアル」が実現しやすくなります。
一方で繁忙期に重なると、制作会社とのやり取りも後回しになりがちで、「途中まで進めて止まってしまった…」「公開がズルズル遅れた…」というケースも少なくありません。

■ リニューアル後の「告知」や「展開」にも集中できる
ホームページをリニューアルしたら終わりではなく、その後に
- SNSでの告知
- メールマガジンでの案内
- 印刷物のURL更新
- 社内外への広報
など、周辺の展開や連携も重要なステップとなります。
落ち着いた時期に制作・準備を終えておけば、余裕を持って告知・プロモーションにも取り組めるため、リニューアル効果を最大限に活かすことができます。
■ “暇な時期にやる”のではなく、“戦略的に落ち着いた時期を選ぶ”
「業務がひと段落したこのタイミングなら動きやすい」
「年末年始や夏前後は比較的時間が取れる」
「新年度や決算に向けて準備しておきたい」
このように、会社の年間スケジュールを見ながら、無理なく取り組める時期をあらかじめ見極めて動き出すことが、スムーズなホームページリニューアルのカギとなります。
忙しい時期に“やらなきゃ…”と焦るよりも、落ち着いたタイミングに“しっかり整える”方が、結果的に費用対効果の高いリニューアルが実現できます。
社内全体の納得感も得やすく、制作パートナーとの連携もスムーズになるため、非常におすすめのタイミングです。
リニューアル時に気をつけるポイント
既存顧客への周知方法
ホームページをリニューアルしたときに忘れてはならないのが、すでに取引のあるお客様へのご案内です。
新規顧客の獲得ばかりに目が向きがちですが、既存顧客にとっても、ホームページは「取引先としての信頼感」を支える重要な接点のひとつ。
「変わったこと」をしっかり伝えないと、混乱や不信感を与えてしまうこともあります。
■ まずは「どんなことが変わったのか」を明確に伝える
ただ「リニューアルしました」と伝えるだけでなく、次のようなポイントを簡潔に伝えることが大切です:
- デザインが見やすくなった
- スマホやタブレットで閲覧しやすくなった
- 製品・サービスの情報がより探しやすくなった
- 会員ページや資料ダウンロードが便利になった
- 操作方法やお問い合わせ方法に変化がある場合はその説明も入れておく
“何が良くなったのか”“どこが変わったのか”を丁寧に案内することで、好意的に受け取ってもらいやすくなります。
■ 周知の手段はいくつかを組み合わせて
顧客層の属性によって好まれるコミュニケーション手段が異なるため、以下のように複数のルートを活用して周知するのが効果的です:
- メールマガジン:最もスタンダード。画像付きでわかりやすく紹介。
- 請求書や納品書に同封するお知らせ:紙ベースでも伝えられる。高齢層や法人向けに有効。
- 電話対応時に一言案内:日々の対応の中で自然に伝えられる。
- 営業担当からの訪問・電話時に案内:個別の対応が可能なBtoBでは特に有効。
- SNSやLINE公式アカウントでの告知:デジタルに強い顧客層へ。
- ホームページ内に「リニューアルのお知らせ」ページやポップアップ表示も忘れずに。
■ リニューアルは「お客様との再接点をつくるチャンス」
実は、ホームページのリニューアルは既存のお客様にもう一度自社の魅力を伝えるチャンスでもあります。
お知らせの中に、
- 改めてのご挨拶
- 最新サービス・人気商品・活用事例の紹介
- SNSやメルマガ登録のご案内
なども盛り込めば、お客様との関係性を深め、再購入・再依頼につなげることもできます。
「リニューアルしました」ではなく、「より便利に・わかりやすくなりました」と伝えるのがポイント。
お客様目線で、丁寧に・わかりやすく案内することで、信頼感のある移行を実現できます。
制作会社との連携とスケジュール管理
ホームページのリニューアルは、見た目や機能の刷新だけでなく、「誰とどう進めるか」が成功のカギを握っています。
特に制作会社との連携やスケジュール管理がうまくいかないと、予定通り公開できなかったり、満足のいかない仕上がりになってしまうことも。
ここでは、実務的なポイントを押さえて進めるためのコツを解説します。
■ まずは目的・ゴールを共有することが最重要
制作会社と最初に打ち合わせをする際、以下のような点を明確に伝えることが大切です:
- なぜリニューアルしたいのか(目的)
- リニューアル後にどんな効果を期待しているのか(目標)
- 想定している公開時期(スケジュール)
- 参考になるサイトや希望イメージ
- 今のサイトで困っている点・改善したい点
この「共通認識」があるかどうかで、進行のスムーズさが大きく変わります。
曖昧なままスタートすると、方向性がズレたり、作り直しが発生したりして時間もコストもかかる原因になります。
■ スケジュールは「余裕を持った逆算型」で組む
ホームページ制作には、以下のような工程があります:
- ヒアリング・要件定義
- デザイン設計(ワイヤーフレーム → デザイン案)
- コーディング(構築)
- テスト環境で確認
- 修正対応
- 本番公開
これに加えて、原稿作成・写真素材の準備・社内確認の時間なども必要です。
したがって、「納期の1.5〜2ヶ月前にはスタート」するのが理想的です。

さらに注意したいのが「社内確認にかかる時間」。
経営層や各部署の承認が必要な場合は、事前に誰が何をチェックするのかも決めておきましょう。
■ 連携をスムーズにするコツ
制作会社とのやりとりでは、次のような点を意識するとスムーズに進みます:
- 窓口(担当者)を一本化する:社内外での情報のズレを防げる
- やりとりの履歴を残す:メールや共有ドキュメントなどで情報を見える化
- 進捗管理ツールを活用:Notion・Backlog・Googleスプレッドシートなどを活用
- 週1ペースの進捗確認:定例ミーティングや報告でズレを早期に発見
■ 最後に:制作会社は「パートナー」として信頼関係を築こう
制作会社を「外注先」ではなく、「一緒にゴールを目指すパートナー」として接することが、より良いリニューアルにつながります。
疑問や不安があればこまめに相談し、できるだけオープンな関係性を築くことが、最終的な仕上がりに大きく影響します。

まとめ – ホームページを進化させるために
定期的なチェックと改善が信頼につながる
ホームページは「作って終わり」ではありません。
むしろ、公開してからが本当のスタート。
定期的なチェックと改善を行うことで、ユーザーからの信頼感や利便性が高まり、ビジネス成果にも直結します。
■ 「放置されたホームページ」は信頼を下げる
ホームページに訪れたときに、
- 最終更新日が何年も前
- お知らせが古いまま
- リンク切れがある
- 掲載されているサービスが現状と合っていない
といった状態だと、「この会社、大丈夫かな?」という不安を抱かせてしまいます。
特に、企業の信頼性をオンラインで判断することが当たり前になっている今、更新のないサイトは「活動していない会社」にも見えてしまいます。
■ 定期的な点検のチェックポイント
ホームページの品質を保つために、次のような項目を定期的(月1〜四半期ごと)にチェックすると効果的です。
- 掲載情報の最新性(商品・価格・スタッフ・会社概要など)
- お知らせ・ブログの更新頻度
- 問い合わせフォームの動作チェック
- 表示崩れ(PC・スマホ・タブレットの各デバイス)
- 外部リンクやSNSリンクの動作確認
- 表示速度やSEO指標(PageSpeed Insightsなどで確認)
これらを定期的に確認・更新することで、サイトの鮮度を保ち、ユーザーに安心感を与えられます。
■ 改善は“小さく・継続的に”でOK
改善というと「大きな変更をしないといけない」と構えてしまいがちですが、実際は次のような小さな積み重ねで十分効果があります:
- よくある質問(FAQ)の追記
- 人気商品への導線を強化
- お問い合わせページの文言をわかりやすく変更
- 実績や導入事例の追加
- スタッフの写真やコメントの更新
こうした小さな改善が、「この会社はきちんと手を入れて運営している」という安心感を生みます。
■ Googleの評価にも影響
SEOの観点でも、定期的な更新・改善はプラスに働きます。
Googleは「価値のある情報を定期的に提供しているかどうか」も評価対象にしているため、放置されたページよりも、更新されているページの方が上位表示されやすくなります。
■ 改善のヒントは「ユーザーの声」にある
改善のネタに困ったら、以下を参考にしてみましょう:
- お問い合わせでよくある質問や相談
- アクセス解析(Google Analytics)で離脱の多いページや滞在時間が短いページ
- SNSや口コミでの反応
- 社内の営業・サポート部門からのフィードバック
ユーザーの行動や声をもとにサイトを見直すことで、より実用的で愛されるサイトに育っていきます。
まとめ
- ホームページの定期点検は「信頼感」を保つメンテナンスのようなもの
- 小さな改善の積み重ねがブランドイメージを強くする
- 情報の更新・操作性の向上はユーザー目線で見ることがカギ
- 放置ではなく「手をかけている姿勢」こそが信頼につながる
プロと相談しながら最適なタイミングを見極めよう
ホームページのリニューアルは、「古くなったから」「上司に言われたから」といったきっかけだけで進めてしまうと、タイミングを間違えて効果が薄れたり、リソースを無駄にしてしまうこともあります。
そうならないためには、Webのプロ(制作会社・Webコンサルタント)と相談しながら、最適な時期と進め方を見極めることがとても重要です。
■ プロに相談することで得られるメリット
制作会社やWebの専門家に相談することで、次のような具体的なメリットがあります:
- 自社だけでは見えない「業界トレンド」や「競合の動き」を教えてもらえる
- 自社のホームページの課題点や改善ポイントを客観的に分析してもらえる
- 公開後の運用まで見据えた実践的なスケジュールを立てられる
- 予算や体制に応じて無理のない進め方を提案してくれる
つまり、「なんとなく」で判断するのではなく、客観的な情報や実績にもとづいた“根拠のある判断”ができるようになります。
■ プロと一緒に確認すべきポイント
タイミングを見極める際には、以下のような観点を制作会社と一緒に確認するとよいでしょう:
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 現在のホームページの問題点 | デザイン・導線・更新性・SEO・表示スピードなど |
| 業界の流れやユーザーの行動変化 | スマホ率の変化、競合サイトのリニューアル状況など |
| 自社のリソース状況 | 担当者の工数・原稿作成の体制・確認フローなど |
| ビジネスのタイミング | 新サービスの立ち上げ、年度切り替え、展示会や繁忙期の前など |
| 予算と実施可能な範囲 | 機能追加やCMS導入の要否などをふまえたプラン設計 |
これらを一緒に整理することで、「やるべき理由」と「今がその時かどうか」が明確になります。
■ 無理に急がないことも成功のポイント
プロと相談していく中で、「今はまだタイミングではない」という結論に至る場合もあります。
それでもOK。
準備期間をしっかり取ることで、社内体制を整えたり、資料を揃えたり、良いデザインの方向性をじっくり検討することができます。
逆に、急ぎすぎて公開後に「こんなはずじゃなかった」とならないよう、“今リニューアルする意義があるのか”を冷静に見極めることが、後悔のないリニューアルにつながります。
まとめ
- リニューアルのベストタイミングは「今すぐ」ではなく「よく考えてから」
- プロの意見を取り入れることで、根拠ある判断と効果的な進行ができる
- 「何のためにリニューアルするのか?」を明確にすることが最初の一歩
- タイミングに迷ったら、まずは気軽に相談してみるのが成功への近道
いかがでしたでしょうか?
日々の業務が忙しく、制作のパートナーも必要なため、どうしても後回しになりがちなホームページ。
しかし、しっかりと計画を立てて、将来のお客様、既存のお客様の課題解決のためにしっかりとしたホームページを作ること、リニューアルして新しい情報を届けることは必須です。
お困りの方、良いパートナーを見つけたいという方はぜひ、一度お問い合わせください。



コメント